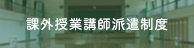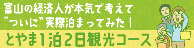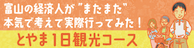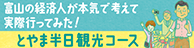事業計画
PLANPlan
2025年度事業計画
ロシアによるウクライナ侵攻から3年が過ぎ、パレスチナ・イスラエル紛争、シリアのアサド政権崩壊など中東地域の地政学的リスクが、国際秩序を大きく揺るがすだけでなく、世界的なエネルギー供給不安、物価上昇を引き起こしている。
また、本年1月に第二期トランプ政権がスタートし、追加関税の発動、国際的な枠組みからの脱退などが矢継ぎ早に発表され、我が国の産業のあり方にも影響を及ぼし、これまで以上に先行き不透明感が高まっている。
このようなVUCAの時代だからこそ、当会としては、地域経済の発展に貢献するという理念のもと、2021年度の当会SDGs宣言に基づき、持続可能な地域社会の実現に貢献する取組みを積極的に推進していかねばならない。
このため、地域が抱える課題解決に向けてリーダーシップを発揮することを念頭に、当会活動の要となる委員会編成を、組織・会務のための委員会と地域課題の解決に資する調査・研究を行う委員会に分け、調査・研究の委員会をこれまでの5つから8つに増やし、活動を深化させていく。
組織・会務のための委員会は、SDGs宣言のパートナーシップに位置づけ、「総務企画委員会」と「交流委員会」を設け、会員増強、会員エンゲージメント向上、他経済団体・アカデミア・行政との連携に、代表幹事以下各役員、委員会も加わり積極的に取り組んでいく。
調査・研究の委員会は、①持続可能な企業経営は「企業経営委員会」と「デジタル推進委員会」、②持続可能な人づくりは「人財育成・活躍委員会」と「教育を考える委員会」、 ③持続可能な地域づくりは「地域創生委員会」と「観光戦略委員会」、「文化芸術委員会」を設け、さらに、今年度から新たに、重要政策課題への迅速な対応を目的とした「代表幹事イニシアティブ委員会」を必要に応じて機動的に設置し、代表幹事の諮問テーマに関し、調査・研究し提言を取りまとめるものとする。
国においては、一極集中を是正し、多極分散型の多様な経済社会の構築に向けて「地方創生2.0」を掲げ、若者や女性にも選ばれる地方づくりを進めるとともに、防災庁などの政府関係機関や企業の本社機能の地方移転、地方における新たな産業の創造を促進することとされている。また、インバウンドが増加するなか、このたび、ニューヨークタイムズの「2025年に行くべき52か所」に富山市が選定された。
こうした社会の変化を好機と捉え、「連携」・「創造」・「行動」をキーワードに会員一人ひとりが積極的に行動し、富山の発展と日本の再生に貢献していきたい。
2024年度事業報告
2024年度は、長らく停滞していた我が国の名目GDPが初めて600兆円を超えた。コロナ禍後の世界的な需要回復や、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う資源価格の高騰を背景とする輸入物価の上昇を起点としたコストプッシュ型の物価上昇に、価格転嫁と賃上げの取組みを政府が強力に推進したこともあり、2024年の春闘では33年ぶりとなる高い賃上げ率が実現した。賃金と物価がともに上昇し、我が国経済は、引き続き緩やかな回復基調にあると考えられるが、本年1月にスタートしたアメリカの第二期トランプ政権の関税引上げ等保護主義政策次第によってはサプライチェーンの分断、高インフレなどが懸念される。
また、2024年元日の能登半島地震から1年と3か月が経過したが、今もなお、事業活動に影響が生じているなど復旧・復興は道半ばであり、さらに昨年9月の豪雨被害や本年2月の大雪被害などが発生し、自然災害への備えと経済・産業活動の基盤となる社会インフラの強靭化が望まれる。
さて、このような状況のなか、2024年度においても当会活動の根幹をなす委員会活動が活発に展開され、3つの委員会が提言を公表した。まず、人財活躍委員会は、「様々な人財が富山で輝ける社会を目指して」と題し、採用活動への行政・企業・経済団体・教育機関の連携強化を求めるとともに、企業活動に多様な人材を活用し、その能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進するよう提言した。教育問題委員会は、「教師と教育現場のチャレンジ支援のために」と題し、「教師力向上」のために私立学校教師を含む県内の教師が、学校関係者以外と交流できる機会を創出することや、中高一貫校及び国際バカロレア認定校の設立について提言した。そして、地域創生委員会は、「つながる富山、共創の未来~エリアリノベーションで描く新たな100年~」と題し、神通川旧河道エリアを若者で賑わう共創の空間とすべく、官官/産学官民が連携した能動的な組織立ち上げを提言した。
次に、各委員会のSDGsの活動状況を紹介する。「持続可能な企業経営」をテーマに、企業経営委員会は、前年度に引き続き、諸課題への対応とあるべき経営者の姿に関して考える、県内企業訪問、経営道場、拡大委員会を積極的に開催した。
「持続可能な人づくり」をテーマに、人財活躍委員会は、「女性活躍」「外国人材の活躍」「兼業副業人材の活用」に取り組むべく、外国人材活用の先進事例視察、外国人留学生との交流事業「TOYAMA KATARAI CAFE」、「留学生向け企業見学会」、「産学官交流会」を行政・大学と連携しながら開催した。また、教育問題委員会は、海外教育事情視察の後継事業「教師と企業人との交流」、国際バカロレア認定校視察、県教育委員会との意見交換会などを開催するとともに、課外授業講師派遣にも積極的に取り組んだ。
「持続可能な地域づくり」をテーマに、地域創生委員会は「魅力あふれる持続可能なまちづくり」実現のための「産学官連携のあり方」「持続可能なエリアマネジメント」「魅力ある都市デザイン」について知見を深めるため、講演会や県外視察などを開催した。また、文化スポーツ委員会は、文化芸術に親しみ、地域文化・スポーツ活動を支援し、地域活性化に貢献することに加え、文化・スポーツによるまちづくりを考えることとして、県内視察やスポーツ及び文化の「同友会の日」を実施した。
また、4つの小委員会(「ESG経営小委員会」「アントレプレナーシップ小委員会」「ウェルビーイング小委員会」「アスリート支援小委員会」)は、知見を深めるための講演会・勉強会の開催、スケッチオーデションプログラムの実施、アスリート支援の仕組みづくりに向けた勉強会・意見交換等に積極的に取り組んだ。